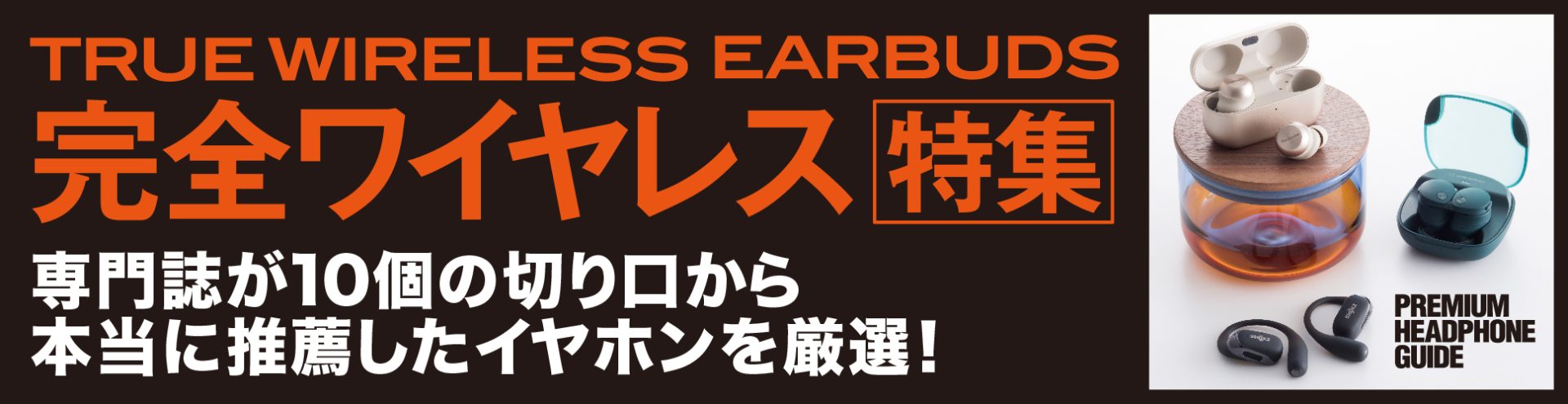ソニーのスタジオモニターヘッドホン「MDR-M1ST」。数多くのスタジオで採用されてきた定番モデル「MDR-CD900ST」以来、約30年ぶりに発売されたスタジオモニターヘッドホンとなる同作は、いまの時代の音楽制作現場の声を徹底的にヒアリングして、ゼロから再構築された現代のレファレンスともいうべきヘッドホンです。その開発背景に岩井 喬氏が迫ります。

- 密閉・ダイナミック型ヘッドホン(モニターヘッドホン)
SONY
「MDR-M1ST」
¥OPEN(実売想定価格¥34,650前後/税込)
1989年の「MDR-CD900ST」の発売以来、約30年ぶりに誕生したモニターヘッドホン。MDR-CD900STと同様、ソニーとソニー・ミュージックスタジオが共同で開発に当たりました。
音楽制作現場と共同開発
いまや国内スタジオの標準モニターヘッドホンとして広く認知されているのがソニー「MDR-CD900ST(以下、CD900ST)」です。CD用にデジタル録音環境が広まりつつあった80年代後半。その新しい器を作るうえで制作サイドのモニタリング環境も見直す必要があるとして、CBS・ソニーの信濃町/六本木スタジオ用として1988年に誕生したのが「MDR-CD900CBS」です。その後、他のスタジオやミュージシャン、コンシューマーへ向けて販売されることになりCD900STとして30年に渡って幅広いユーザーに愛用されてきました。

-
密閉・ダイナミック型ヘッドホン(モニターヘッドホン)
SONY
「MDR-CD900ST」
¥24,860(税込)
ソニーと、数々の名盤を生み出してきたソニー・ミュージックが共同で開発したモニターヘッドホン。1982年、CDの出現によって、楽曲制作においては、低域の拡張や広いダイナミックレンジ、繊細な高域表現など、幅広い音楽表現が可能になりました。そんな背景のもと、CDに対応したヘッドホンとして開発されたのが本機です。
しかし、いまや192kHz/24bitやDSDといったプロの制作現場で聴くことのできるクオリティと同等のハイレゾ音源がコンシューマーでも楽しめる時代。CD900STとは違う現在の環境に即したモニターヘッドホンが求められるようになってきました。そうした背景のもと、2019年、ソニーと乃木坂にあるソニー・ミュージックスタジオを運営するソニー・ミュージックソリューションズとの共同開発モデルとして「MDR-M1ST」が発売されました。
このMDR-M1ST開発に当たった株式会社ソニー・ミュージックソリューションズのレコーディングエンジニアである松尾順二氏と、ヘッドホン設計に携わったソニー株式会社の潮見俊輔氏より開発経緯を伺う機会を得ました。まずはその開発のきっかけから教えていただきましょう。
「1989年にCD900STが開発されて以降、新たに登場した素材や技術によって現在のヘッドホンの在り方も大きく変わっています。ヘッドフォン祭の盛況を目にしたこともあり、そうした進化を生かした新しいモニターヘッドホンを作りたいと考えていました」(松尾氏)。
では実際にどういうものにするのか、はじめはCD900STをベースに高域特性を伸ばしたハイレゾ化も試作したそうですが、〝そういうことではない〟と一蹴されたそうです。
「それでは作る意味がない。むしろCD900STを意識しないということをはじめの段階で決めました。まず、音質面で歪みを少なくしてほしいという点と、装着感をCD900STよりよくしてほしい、最高の着け心地をとお願いしましたね」(松尾氏)。

- 右がおよそ35年にわたって業界標準として君臨し続ける名機MDR-CD900ST、左がMDR-M1ST。可聴帯域を超えるハイレゾの音域をダイレクトかつ正確に再現すべく、約4年半の歳月をかけて、全く新規に開発された現代版スタジオモニターです。
歪みが少なくて音が近い。快適なフィット感も追求したい
2015年頃、松尾氏と潮見氏、さらにスタジオの機材メンテナンスを手掛けるテクニカルエンジニアの堺清氏が開発メンバーに加わりました。ヘッドホンの保守管理面からの観点も踏まえ、構造や取り回し面についても議論が重ねられ、2017年頃に大枠が決まったといいます。
「歪みのない音を目指すと刺激感も少なくなり、対象とする音が遠くから聴こえてくるような耳当たりのよい傾向になります。ただ、その遠くから聴こえてくるようではだめで、ミュージシャン、特に歌い手はモニターヘッドホンから聴こえてくる自分の声が遠くに聴こえると〝声が出ていない〟と捉え、頑張りすぎて声を張り出してしまう。結果として録音がうまくいかないということも起こりうるわけです。だから耳元で的確に近い位置で聴こえてきてほしいのですが、その点の調整に時間がかかりましたね」(松尾氏)。
「ヘッドホンの音の印象はイヤーパッドの構造でも大きく変わるのですが、当然装着性にも影響します。装着性をよくしようとパッドの構造を変えていくと、音の距離感を含めた印象も変わっていってしまう。音の距離感の印象について会話をしているとき、エンジニアの皆さんは〝こんな感じ〟の音、とハウジングを耳に押し付けて聴いていたんです(笑)。この装着状態も参考にして設計していきました。ヘッドバンドの構造を含め、ゼロベースで設計しましたが、側圧はCD900STよりも高いものの、格段に装着性のよいものに仕上がりました」(潮見氏)。

- ソニー・ミュージックスタジオが誇るレコーディングエンジニアたちの声をもとに設計された、新しいスタジオモニター、MDR-M1ST。デザインこそMDR-CD900STのイメージを踏襲していますが、その中身は全くの新設計。それぞれに異なるサウンドチューニングになっています。
松尾氏が低歪みにこだわった理由は現在の録音環境が整備され、低歪になってきたことにあるそうです。ただマイクは発展途上で、100kHzまで収録できるものはわずか。しかし今後はそうした広帯域対応のマイクも珍しいものではなくなると踏まえ、ヘッドホンも当然そうした環境に揃える必要があると考えたとのこと。ヘッドホンの歪みが多ければ、付加された歪みの分、音がぼやけてしまいます。そして歪みが少ないからこそ音量を小さくしても細部まではっきりと状態を掴みやすく、入力された音の不要な歪みも判別しやすくなります。最終的にはソニー・ミュージックスタジオのエンジニアである鈴木浩二氏、内藤哲也氏、原剛氏、野口素弘氏にも音作りに参加してもらい、完成度を高めていきました。
ドライバーユニットの振動板は従来と同じ40mmですが、その細部のつくりは全く違います。振動板素材は入手しやすい汎用の樹脂フィルムですが、これはMDR-M1STが十年以上販売できることを見据え、長期入手できる素材を考慮したことによるそうです。

- プロフェッショナル向けモデルらしく、メンテナンスしながら長く使えるように堅牢な設計になっており、さまざまな交換パーツが用意されています。また、CD900STと同じく、M1STも大分県にあるソニー・太陽株式会社で徹底的な品質管理のもと製造されています。
中低域に重厚感があり、余韻は消え際まで鮮明
実際にMDR-M1STをソニー「NW-WM1Z」に接続して聴いてみると、CD900STのエッジの強いサウンドとは一線を画す、滑らかで落ち着いた音調が印象的です。脚色がない分、高域の煌きも控えめで、ピアノの響きも重厚感があり、アタックの繊細さも丁寧に描き出します。ボーカルはボディの厚みが自然に表現され、口元はスッキリと分離よくフォーカスされた定位を見せます。低域のエナジーもロスなく引き出し、ベースとキックドラムとの描き分けも適切です。オーケストラの音場は広く、余韻の響きの豊かさも階調よく描きます。別売ケーブル「MUC-S12NB1」を使ってのバランス駆動では、さらに分離よくキリッとしたボーカルの定位感やリヴァーブのリアルさ、音場の静けさがよりよく描かれています。リズム隊のアタックも締まりよく見通しが深いです。密度感も高く、質感はより丁寧に表現。余韻の消え際も鮮明です。
「スタジオでもすでに導入していますが、みなさん違和感なく使用されています。聴きやすくなったねという意見も聞きますね。デザインはソニー・ミュージックソリューションズのデザイナーにも参加してもらい、デザイン面もコラボしています。アイコニックな点は継承しつつ、まったく新しい時代のモニターということでM1の名を与えました。ハイレゾ音源を作っている同じツールで同じ音源を楽しめる。そこに込めた意図も伝わりやすくなると考えています」(松尾氏)。
「『MDR-Z1R』と並行しながらの設計・開発でしたが、私も音響設計に携わるものとして大きく成長できた製品になったと思います。〝潮見といえばこれ〟という代表的なアイテムの一つになったと自信を持っています」(潮見氏)。
MDR-M1STは一般的なコンシューマー用モデルよりも数倍高い耐久性も実現し、80kHzまでの広帯域再生能力も持たせた、新世代を担うスタジオモニターヘッドホンです。色付けのないナチュラルな音は入力された信号をストレートに引き出すために必要不可欠な要素。CD900STとは違う個性として、共に切磋琢磨しあえる存在になっていくでしょう。
SPEC
SONY「MDR-M1ST」
●型式:密閉ダイナミック型 ●ドライバー口径:40mm ●再生周波数帯域:5~80,000Hz ●インピーダンス:24Ω ●ケーブルの長さ:約2.5m ●質量:約215g(ケーブル含まず)